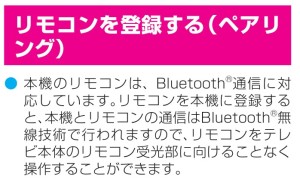新しいTVで気付いたこと(その2) ― 2026年01月23日
今回は、「新しいTVで気付いたこと」の第2弾として「電子番組表のch並び」に関する話題です。
購入直後の地デジのch並びはこのようになっていました。
この並びは以前のアナログch時代を思い出させるのですが、決して古いままという訳ではないみたいです。Windows11のCOPILOTに訊いたところ、次のような回答を得ました。
~~~~~
REGZA の地デジ番組表(EPG)のチャンネル並びが「アナログ時代の順番」に見えるのは、REGZA が “放送局の物理チャンネル順(受信順)” を基本に並べているためです。これは多くのテレビが採用している方式で、東芝だけの特殊仕様ではありません。
~~~~~
このような回答を得たのであきらめるしかないのかなと思っていたら、必ずしもそうではないみたいです。TV本体の取扱説明書より詳細な「リモコンの取扱説明書」を調べていたら、次のような記述がありました。
※ リモコン取扱説明書からの引用です
早速サブメニューのキーにより設定し直してみました。結果はこのようになり、新聞の番組欄と同じch並びになりました。
電子番組表に関しては、もう一つ気になることがあります。それは、BS放送のch並びです。購入直後はこんな感じになっていました。
すでに放送が終了しているBS103が空欄のまま表示されています。このような表示は気に入らないので何とかしたいと思い、サブメニューのキーで方法を探ったところ、「チャンネルスキップ設定」というメニューがあり、BS103をスキップするように設定すると問題が解決できそうなことが分かりました。

BS103をスキップするように設定すると、電子番組表がこのように変わりました。
これで、気になっていたことはすべて解決です。
ほかに、サブメニューの中には「表示ch数」を変えたり「番組概要の表示」を消したりといった項目もあるみたいです。今のテレビはソフトの設定次第でいろいろ変えられるみたいですが、内容が複雑すぎて使いこなすのが大変ですね。
新しいTVで気付いたこと(その1) ― 2026年01月17日
新年早々にテレビを更新しました(詳しくはこちら)。新しいテレビはだいぶ進化しており、使いこなせるようになるまではいろいろ新しい発見がありそうです。そこで、「新しいTVで気付いたこと」というタイトルでシリーズものを組んでみようと思います。
第1弾の今回は、「リモコンの通信方式について」です。
いろいろな家電でリモコンが使われていますが、そのほとんどは“赤外線による通信方式”を使っています。これまで使っていた液晶テレビも赤外線方式のリモコンでした。一方、新しいテレビには“Bluetooth”という通信機能が標準装備されており、例えばワイヤレスイヤホンなどと接続(ペアリング)すればテレビの音声をイヤホンで聴くことができます。
このBluetoothの通信機能を利用して、新しいテレビではリモコン操作もできるようになっています。Bluetooth通信によるリモコン操作だと何が良いのかというと、リモコンをいちいちテレビに向けなくてもリモコン操作ができるんです。これは使ってみると非常に便利であることを実感します。
テレビの取扱説明書には、次のように説明してありました。
ただし、テレビが待機モード(オフ状態)のときにはテレビ本体のBluetooth機能もオフになっているので、テレビをオン状態にするときだけは“赤外線通信”を使う必要があるようです。リモコンには赤外線通信かBluetooth通信かが識別できるようなLED表示が備えられており、赤外線通信の場合には赤色のLEDが、Bluetooth通信のばあいには青色のLEDが点滅します。
実際にLEDが点灯しているときにはこんな感じになります。
もちろん、Bluetoothのペアリングをオフにすれば通常の赤外線リモコンと同じになりますが、一度Bluetooth通信を使ってしまうとペアリングをオフにするなんてことは考えにくいです。
高圧洗浄機から水漏れ ― 2025年10月16日
2018年11月に購入した高圧洗浄機(ケルヒャー製K2 Classic)を使っていたら、本体底面から水漏れしているのに気付きました。それがポタポタという漏れかたよりも多い状態でした。このような状態で使い続けたら内部の電気回路を濡らすことになって危険なので、何とか修理できないものかと挑戦することにしました。
しかしながら、ケルヒャー製品はユーザーが安易に分解できないようにするためか、特殊ねネジを使っています。トルクスネジという頭が5角形の穴の形状になっています。普通の6角レンチではこのネジを回すことができません。
でも、趣味で集めたいろいろなドライバーセットを探したら“ありました!”。

早速分解してみたところ、内部はシンプルな構造になっていました。

この状態で水道に接続して水漏れ箇所を調べてみました。当初は給水の接続部あたらかな?と想像していたのですが、接続部はまったく問題ありませんでした。

そこで、さらに分解して高圧ポンプを確認したところ、高圧を発生させるプランジャー部分から漏れていることが分かりました。

プランジャー部分からの漏れでは素人の手に負えません。諦めるしかなさそうです。
このままの状態で使い続けると、電気回路に漏れた水が回り込んで非常に危険ですので、この高圧洗浄機は廃棄することにしました。
次に購入するときには、ケルヒャー製ではなく国内メーカーのものだったらどうかな?と考えています。我が家では高圧洗浄機を頻繁に使うわけではないので、しばらく次の機種について検討してみようと思います。
血圧計からスマホにデータ転送する方法 ― 2025年10月07日
このたび購入した血圧計(オムロン製HCR-7204T)は、Bluetoothという通信方式を使って血圧計からスマホへのデータ転送ができるようになっています。この転送方法(手順)がややこしいのでなかなか理解できなかったのですが、いろいろ試してようやくやり方が理解できました。今回のブログでは、その方法について紹介したいと思います。
データの転送にあたっては、「血圧の測定データをスマホに転送する」ための操作をすべてスマホ側で行います。まず、スマホアプリ(OMRON CONNECT)のホーム画面上部にある両矢印(図中の赤丸)をタップします。

このとき、スマホ側のbluetoothがオフになっていると、「OMRON CONNECTが機器と通信できるようにbluetoothをONにしますか?」というメッセージが表示されるので「OK」をタップします。次に「OMRON CONNECTがbluetoothをONにしようとしています」メッセージが表示されるので「許可」をタップします。これでスマホのbluetoothがON状態に切り替わります。
スマホのbluetoothがON状態に切り替わったら、次に血圧計とスマホの通信接続(ペア設定)の操作になります。まず、ホーム画面にある両矢印を再びタップします。すると「データ転送」のダイアログが表示されるので、血圧計の型番の部分をタップします。

「ペアリクエスト」のダイアログが表示されたら、「ペア設定して接続」をタップします。すると確認画面が出て「このデバイス(血圧計の意味)をペアに設定しますか?」と表示されるので、「ペア設定する」のボタンをタップします。
これでデータ転送の準備ができたことになります。再びホーム画面に戻りますので、画面上部の両矢印をタップします。再度「データ転送」のダイアログが表示されるので血圧計の型番の部分をタップします。するとダイアログ画面の下に「転送中」と点滅表示されて転送が始まります。
転送が完了すると「転送完了」という表示に切り替わります。これで「血圧データの転送」は完了です。
転送が無事にできたかどうか確認するには次のように操作します。OMRON CONNECTアプリのホーム画面上で、血圧の部分をタップして血圧データの画面に切り替えます。
次に画面上部の縦にドットが3つ並んだ部分をタップすると、メニューが表示されますので「測定結果一覧」を選択します。一覧表の「血圧の値」や「日付・時刻」から、データが無事に転送されているか確認できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回いろいろ試してみて気付いたことは次の通りです。
●この一連の作業において、血圧計の電源が入っていなくても電池が入れてあれば
問題なく転送できるようです。
● アプリは、この作業以前にスマホに転送してあったデータを参照して、追加分だけを
転送するようです。
● 血圧計のほうには最大14回分の測定データしか保存されないので、転送データの量は
最大でも14回分です。14回を超えると以前のデータは順次上書きされてしまいますので、
それ以前にスマホに転送する必要があります。
● 取扱い説明書によれば、OMRON CONNECTアプリの設定で、画面データ転送を自動的に
行うこともできるようですが、自動的に行われるタイミングが分かりにくいので、手動操作で
確実に転送するのが良さそうです。
なお参考までに、自動転送の機能をオフにする方法を以下に記します。
● OMRON CONNECTアプリの画面を「ホーム」から「機器」に切り替え、
血圧計(HCR-7204T)をタップします。
● 血圧計に関する設定画面が出たら、「自動データ転送」のスイッチをOFFにして
画面上部にある「保存」をタップします。