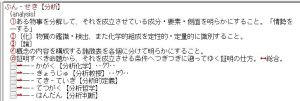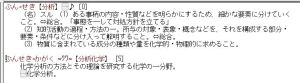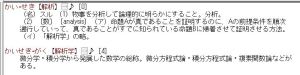レッグウォーマーの試み ― 2016年01月13日
今朝はこの冬一番の冷え込みとなり、最低気温が-4.5℃まで下がりました。ここまで下がるとさすがに暖房の効きが弱く、いつもと同じ時間にエアコンをタイマー作動させたのですが、起床時に部屋があまり暖まっていませんでした。

※ この図は、NHKのデータ放送からの引用です。
散歩に出かける8時過ぎになっても玄関先は-1℃でした。それでも頑張って午前の散歩で何とか2万4千歩ほど歩いてきました。服装としてはいつもより防寒対策を強化し、セーターおよびニット帽を着用したので、上半身はあまり寒く感じなかったのですが、下半身はズボンだけでアンダーウェアを履かなかったので「ふくらはぎ」が寒気に晒されてあまり力が入りませんでした。
なぜアンダーウェアを履かなかったのかというと、以前に履いて散歩に出かけたら途中で暖かくなっても、脱ぐに脱げず下半身が蒸れて苦労したことがあったからです。寒い分には一生懸命歩けば身体が暖まるので何とかなるのですが、蒸れるくらい暖かくなるとどうしようもありません。なので、終日にわたって本当に冷え込むとき以外には履かないようにしているんです。
それで、歩きながら「散歩時の下半身の寒さ対策として何か良い方法はないものか」と考えて、ふと世の中には「レッグウォーマー」なるものがあることに思い当たりました。
早速、午後の散歩でレッグウォーマーを買い求めてきました。こだわりのシルク入りの製品ですので、薄手の生地でも暖かそうです。
散歩に出かける8時過ぎになっても玄関先は-1℃でした。それでも頑張って午前の散歩で何とか2万4千歩ほど歩いてきました。服装としてはいつもより防寒対策を強化し、セーターおよびニット帽を着用したので、上半身はあまり寒く感じなかったのですが、下半身はズボンだけでアンダーウェアを履かなかったので「ふくらはぎ」が寒気に晒されてあまり力が入りませんでした。
なぜアンダーウェアを履かなかったのかというと、以前に履いて散歩に出かけたら途中で暖かくなっても、脱ぐに脱げず下半身が蒸れて苦労したことがあったからです。寒い分には一生懸命歩けば身体が暖まるので何とかなるのですが、蒸れるくらい暖かくなるとどうしようもありません。なので、終日にわたって本当に冷え込むとき以外には履かないようにしているんです。
それで、歩きながら「散歩時の下半身の寒さ対策として何か良い方法はないものか」と考えて、ふと世の中には「レッグウォーマー」なるものがあることに思い当たりました。
早速、午後の散歩でレッグウォーマーを買い求めてきました。こだわりのシルク入りの製品ですので、薄手の生地でも暖かそうです。
今朝のようにかなり冷え込んだときには、このようにレッグウォーマーでふくらはぎを保護します。

散歩途中で暖かくなってきた場合には、このようにレッグウォーマーをずり下げれば良いわけです。

次の冷え込んだ日にはレッグウォーマーを着用して、その効果と便利さを確かめてみようと思います。
梅の開花 ― 2016年01月14日
散歩途中に梅林があり、そこの梅の木が開花していました。
まだ開花したばかりで2分咲きといったところですが、それにしてもまだ1月中旬なのにもう開花とは。。。。。これも温暖化の影響なのでしょうか。
今朝の最低気温は氷点下1度ほどで冷え込みはそれほど厳しくなかったのですが、昨日購入した“レッグウォーマー”を早速試してみることにしました。
歩き始めて身体が温まるまでは、ふくらはぎが冷えることなく、なかなか快適でした。でも、11時を過ぎた頃には気温が上がり風もなかったため、暑苦しさを感じるようになりました。
そこで、レッグウォーマーをふくらはぎから足首にずり下げたところ、まるでレッグウォーマーを着けていないかのような感じになり、暑苦しさを感じることなく歩くことができました。レッグウォーマーをずり下げるのも簡単にでき、ほんの数秒でできます。
今回の試みは“大成功”でした。今後も冷え込んだ朝にはレッグウォーマーを着用して散歩に出かけることにしたいと思います。
散歩による地球一周旅行 《その10 》 ― 2016年01月18日
昨年の1月半ばにアメリカ東海岸を離れ、大西洋横断を始めてからちょうど1年になります(詳しくはこちら)。
1年かけて大西洋を横断し、ようやく地中海の入口近くまで辿り着きました。現在位置は地中海側に面したポルトガル西端の“サンビセンテ岬”から100kmほど南下した海上(西経約9度)です。
1年かけて大西洋を横断し、ようやく地中海の入口近くまで辿り着きました。現在位置は地中海側に面したポルトガル西端の“サンビセンテ岬”から100kmほど南下した海上(西経約9度)です。
※ 正確には、地中海は“ジブラルタル海峡”から東側を指すのだそうですが、ここでは便宜的に
「地中海の入口近く」という表現にしました。
現在位置を拡大したのが次の地図です。これまでのブログで紹介した“アゾレス諸島(詳しくはこちら)”や“マデイラ諸島(詳しくはこちら)”との位置関係も分かると思います。
「地中海の入口近く」という表現にしました。
現在位置を拡大したのが次の地図です。これまでのブログで紹介した“アゾレス諸島(詳しくはこちら)”や“マデイラ諸島(詳しくはこちら)”との位置関係も分かると思います。
次の写真はポルトガル南西端にある“サンビセンテ岬”から見た灯台と大西洋です。この灯台は19世紀半ばに建設されたのだそうです。この岬には観光客がけっこう訪れるようです。
世界一周旅行の進路に“ポルトガル”は入りませんが、せっかくですので首都“リスボン”にも触れておきたいと思います。
リスボンは都市内に約55万人、都市圏に約300万人の人口をかかえており、ポルトガル全体の人口の約27%が都市圏にいるのだそうです。市内の景観はこんな感じです。オレンジ色の屋根がヨーロッパを感じさせますね。
写真中央の建物は“ジェロニモス修道院”で、世界遺産になっているのだそうです。
サンビセンテ岬から東に30kmほど行ったところには、“ラゴス”という街があります。ラゴスは国際的リゾート地になっており、外国とりわけ英国からの観光客が多いようです。参考までに、“ラゴス”という地名はアフリカの“ナイジェリア”にもあり、そちらのほうがよく知られているようです。
これから先はいよいよ地中海突入です。ジブラルタル海峡まであと280kmほどなので、次回の世界一周旅行ブログでは“ジブラルタル”周辺を話題に取り上げたいと思います。
~ ~ ~ ~ ~
今後の日本までの経路は次のようになります。
ヨーロッパにはほとんど上陸することなく、アフリカの一部、イタリア南部、ギリシャ、トルコなどを通って、中東北部に入ることになります。
日本に到着するまでには、経度にすると約150度の移動なります。ちなみに、大西洋横断(約65度の経度変化)に1年ほどかかりましたので、日本に戻るまでこれから2年以上かかる計算になります。世界一周旅行は当分の間楽しめそうですね。
【註】 本ブログにおける写真や地図はGoogleマップからの引用です。
また、地域の情報はWikipediaからの引用です。
“分析”と“解析”の使い分け ― 2016年01月22日
テレビを観ていると、ニュース番組などで“分析”や“解析”という用語がよく使われます。とりわけ、事故があった場合などには多用されるようです。
私は技術屋なので、何となくなのですが“分析”と“解析”を以下のように使い分けるようにしています。
【分析】 データを細かく分けて整理することにより、対象とする事象の特性を見出すこと
【解析】 データを用いて対象とする事象を理論的に明らかにすること
しかしながら、ニュース番組等では“分析”や“解析”という用語をどのように使い分けているのか、私には良く理解できません。英語では両者とも“analysis”となるので、ザックリ言えば“分析”や“解析”のどちらでも良いのかも知れませんが、私の使い分けと異なる使い方をしたアナウンスを聴くとどうも違和感を感じてしまいます。
そこで、辞書で両者の違いを調べてみることにしました。広辞苑(第4版)と大辞林によれば、それぞれ以下のように説明されていました。
【分析】
◆広辞苑(第4版)
私は技術屋なので、何となくなのですが“分析”と“解析”を以下のように使い分けるようにしています。
【分析】 データを細かく分けて整理することにより、対象とする事象の特性を見出すこと
【解析】 データを用いて対象とする事象を理論的に明らかにすること
しかしながら、ニュース番組等では“分析”や“解析”という用語をどのように使い分けているのか、私には良く理解できません。英語では両者とも“analysis”となるので、ザックリ言えば“分析”や“解析”のどちらでも良いのかも知れませんが、私の使い分けと異なる使い方をしたアナウンスを聴くとどうも違和感を感じてしまいます。
そこで、辞書で両者の違いを調べてみることにしました。広辞苑(第4版)と大辞林によれば、それぞれ以下のように説明されていました。
【分析】
◆広辞苑(第4版)
◆大辞林
【解析】
◆広辞苑(第4版)
◆大辞林
広辞苑および大辞林とも、「ある事象を研究(探求)するのに理論的なアプローチがある場合」を“解析”としているようです。そのような説明に基づけば、例えば航空機事故において「フライトレコーダーに記録されてデータから事故原因を究明するような場合」には“分析”という用語を使うのが適切なのでは?と思われます。
でも、分析と解析を英訳すれば両者とも“analysis”となるので、技術論文ならいざ知らず、テレビ報道における使い分けを気にするのは少々神経質すぎるかもしれませんね。
形容詞は語尾が“い”? ― 2016年01月27日
最近の若者言葉で形容詞を短くする表現方法があるようです。例えば「ウマッ(うまい)」、「マズッ(まずい)」等々。このような用法は形容詞に対して使われるようです。
このような用法を耳にして、ふと「そう言えば形容詞って語尾が“い”になるのかな?」と思いました。考えてみれば、「大きい、小さい、高い、低い、深い、浅い、暑い、寒い、甘い、辛い、しょっぱい、酸っぱい、痛い、……」のように、思いつく形容詞はすべて語尾が“い”になっています。
形容詞の語尾が“い”になるのは文法的な法則なのかネットで調べました。その結果、次のようなことが分かりました。
① 活用形として最後に「~ない」を付加する場合、語尾の“い”が“く”に変わるのが形容詞
<例> 大きい⇒大きくない、高い⇒高くない、暑い⇒暑くない
② 用法として、「~だ」をつけると意味が通らなくなるのが形容詞
<例> 赤い⇒赤いだ(×)、痛い⇒痛いだ(×)
ここで、「きれい」という言葉は語尾が“い”になっていますが、上記①に照らしてみると「きれいくない」となって不自然です。また上記②に照らすと「きれいだ」となり自然な使い方になります。これは「きれい」という言葉が形容詞ではないことを示しているのだそうです。ちなみに「きれい」という言葉は形容動詞なのだそうです。
ネットの情報の最後には、「この程度の知識は中学生レベルだよ~ん」とのコメントがありました。この歳になって、このようなことも理解できていなかったなんて.......。
このような用法を耳にして、ふと「そう言えば形容詞って語尾が“い”になるのかな?」と思いました。考えてみれば、「大きい、小さい、高い、低い、深い、浅い、暑い、寒い、甘い、辛い、しょっぱい、酸っぱい、痛い、……」のように、思いつく形容詞はすべて語尾が“い”になっています。
形容詞の語尾が“い”になるのは文法的な法則なのかネットで調べました。その結果、次のようなことが分かりました。
① 活用形として最後に「~ない」を付加する場合、語尾の“い”が“く”に変わるのが形容詞
<例> 大きい⇒大きくない、高い⇒高くない、暑い⇒暑くない
② 用法として、「~だ」をつけると意味が通らなくなるのが形容詞
<例> 赤い⇒赤いだ(×)、痛い⇒痛いだ(×)
ここで、「きれい」という言葉は語尾が“い”になっていますが、上記①に照らしてみると「きれいくない」となって不自然です。また上記②に照らすと「きれいだ」となり自然な使い方になります。これは「きれい」という言葉が形容詞ではないことを示しているのだそうです。ちなみに「きれい」という言葉は形容動詞なのだそうです。
ネットの情報の最後には、「この程度の知識は中学生レベルだよ~ん」とのコメントがありました。この歳になって、このようなことも理解できていなかったなんて.......。